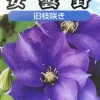早咲き大輪系のクレマチスは、晩春から秋まで大輪の花を楽しめる三季咲きの品種です。旧パテンス系と旧フォーチュンから構成される為、主に旧枝咲きタイプが主流で、冬の剪定は弱剪定で行います。さらに、新旧両枝咲きタイプも増えています。花の色は多くが紫系統で、青紫赤紫が一般的で、その後にピンクや白など淡い色が続きます。花の形状は車形です。
早咲き大輪系の情報や育て方を纏めています。
早咲き大輪系の解説
早咲き大輪系は旧パテンス系と旧フォーチュン(Fortunei)系から構成されます。
パテンス系の栽培品種は、直接的または間接的に、主に C. patens から派生しました。
パテンス系は春に前年の枝に花を咲かせ、夏または初秋に今年の成長に再び花を咲かせるのが特徴でした。
旧フォーチュン(Fortunei)系(フロリダFlorida系とも呼ばれますが、C. floridaとは関係がない)は、前年の春の成長で開花する、八重または半八重の花を持つ品種で構成されていました。
交配により、元の系統を維持することが不可能になり、早咲き大輪系と遅咲き大輪系に分類する事になりました。
早咲き大輪系に含まれる旧系統リスト
- パテンス系(patens)
- フォーチュン系(Fortunei)
パテンス系について
パテンス系のクレマチスは、日本、朝鮮半島、中国東北部から南部に自生していました。
日本では「風車(カザグルマ)」と呼ばれ、江戸時代にシーボルトやロバート・フォーチュンがヨーロッパに持ち帰ったことがきっかけで、ヨーロッパで品種改良が始まりました。
ヨーロッパで品種改良が進んだパテンス系の親種は日本の原種「カザグルマ」であり、「カザグルマ」と交配されたグループをパテンス系と分類しました。
現在では、他品種との交配が進み品種分類を維持できなくなってきた為、大輪で4月頃に咲く事から早咲き大輪系に分類されています。
大輪で華やかさを彩る女王にふさわしいクレマチスです。最も改良が進んでいる品種なので、様々な色から一重から八重まで好みの品種が見つけることができます。
殆どが一季咲きですが、剪定すれば秋も開花する四季咲き性の高い品種もあります。
日本が誇るクレマチスの原種の絶滅危機
江戸時代にシーボルトやロバート・フォーチュンが日本から「カザグルマ」をヨーロッパに持ち帰った事で、早咲き大輪系の育種が始まりました。
パテンスの特徴として変異が起きやすい為、「雪おこし」などのように八重に変異して派生した品種もあります。
「カザグルマ」は自生地でも生育地の破壊や園芸用の盗採などにより数が少なくなり、国は天然記念物、準絶滅危惧種の指定としました。
現在、貴重な自生地では人が立ち入らないよう保護されている場所もあります。
「カザグルマ」が日本の原種と世界に誇れるよう、自生地での盗採は絶対にやめましょう。
特徴
習性とサイズ
早咲き大輪系クレマチスは、異なる品種によって成長特性が異なりますが、一般的に広がる性質を持ち、高さは約1.8〜3メートル(6〜10フィート)に達することがあります。
葉
葉は緑色で、浅裂きまたは羽状になることがあります。
花
大輪の花は、(5〜)10〜22(〜29)cmの範囲内を指します。※カッコは誤差の範囲内
花の直径は6〜10インチ(約15〜25センチ)にも達し、星型で一重、半八重、または八重で、白から深い紫や青などさまざまな色があります。
特に注目すべきは、花の中心部にある雄しべが、花の他の部分と異なる色や形を持つ「対照的な雄しべ」を持っていることです。この対比が、クレマチスの花に深みと視覚的な魅力をもたらしています。
パテンス(C. patens)やラヌギノーサ(C. lanuginosa)の自然な花形(直径12~15cmの大きな花を上向きに咲かせる)に近い傾向があります。
育て方
ツルの先端には日が当たり、根元が日陰であることか理想です。
日当たり
クレマチスは日当たりの良い場所を好みますが、部分的な日陰でも育つことができます。
土壌
肥沃で湿度が保たれ、かつ十分な排水がある土壌が理想的です。しかし、極端な乾燥や土壌中の水分過多は避けましょう。
夏の乾燥
特に夏になると、土壌が乾燥しないように注意が必要です。クレマチスは乾燥した土壌を好まず、地道な水分供給が必要です。
耐陰性
日陰の場所ではクレマチスが花を育てるのが難しいため、できるだけ日光を受ける場所を選びましょう。
耐寒性
一般的に耐寒性が強く、ほとんどの品種は米国農務省のゾーン4から11で繁茂します。
クレマチスがゾーン4から11で繁茂するということは、この植物が寒冷な地域から温暖な地域まで幅広い気候条件に適応できるということを示しています。したがって、多くの地域でクレマチスを育てることができます。
開花時期
5月から10月の晩春から秋にかけて大輪を咲かせます。
早咲き大輪系クレマチスは、古い枝で遅春から初夏にかけて非常に豪華に咲きます。一部の品種は新しい成長時に遅い夏や初秋にも花を咲かせることもあります。
咲く枝
春に前年の伸びた枝に花を咲かせるので、旧枝咲きです。
剪定と剪定時期
旧枝咲きなので、剪定方法は弱剪定です。
通常、早咲き大輪系クレマチスは、前年の新枝で5月から6月に花を咲かせ、夏の新しい成長で再び花が咲くことがあります。剪定は花後に行われ、最良の花を楽しむために軽く行うことが一般的です。
花後の剪定
花が終了したら、古い花を取り除く軽い剪定を行うことがおすすめです。
春の剪定
春には、古くなった茎を地面から30cmの高さで切り戻し、新しい成長を促します。
冬の剪定
寒冷地域では冬に、クレマチスの茎を地面から約30cmの高さまで切り戻し、寒さから保護します。
人気ランキング
早咲き大輪系のクレマチスの各品種ページで【いいね】と、育てやすさの【評価】をランキングにしました。
早咲き大輪系の人気品種と、育てやすい品種が分かりますので、購入の際の参考にしていただければと思います。
早咲き大輪系の品種一覧
お知らせ:reCAPTCHA機能導入のお知らせ
スクレイピング対策およびサーバー負荷軽減のため、reCAPTCHA機能 を導入しました。
「もっと見る」ボタンをクリックすると 15件ずつ 追加表示される仕様となっています。
一定回数クリックすると 全件表示 も可能ですが、環境によっては表示に時間がかかる場合があります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。